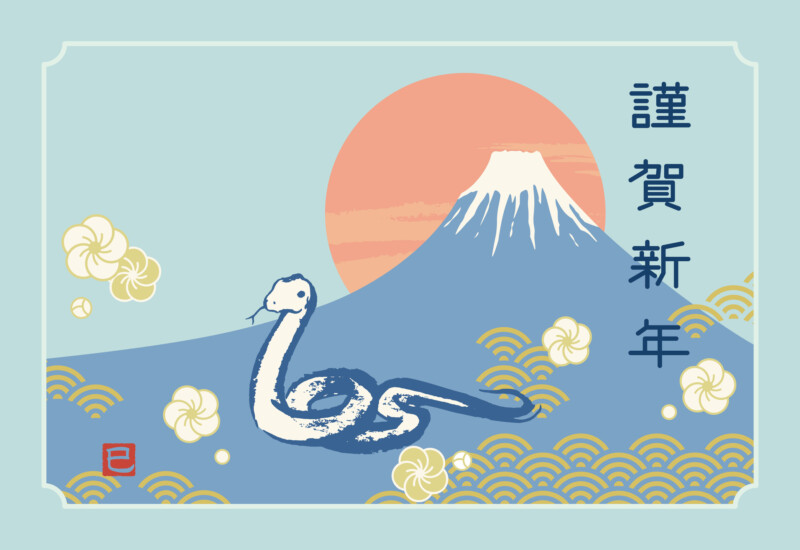本講座の目的と手順について
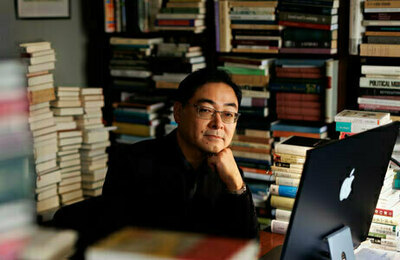
本講座(2025年2月8日より始まる「映画は社会変革にどう貢献できるのか、将基面貴巳教授とともに考える講座」)の究極的な目的は、二つあります。一つは、拙著『従順さのどこがいけないのか』に示されている論点を、抽象的な理解にとどめず、具体的な状況に即して把握することです。そのために、映画を教材として使用します。もう一つの目的は、受講者の方々が「従順さを克服」したり「不正と対決」したりするよう人々をインスパイアする演劇・映画企画を立ち上げるためのヒントを提供することにあります。この目的を達成するために、各セッションでは三つの課題に取り組みたいと思います。
1 話題とする映画について、私なりの政治思想的な観点からの解釈とその解釈に用いる概念や理論を理解いただくこと。
「理解」いただくのは重要ですが、私の理解が「正しい」解釈だと言いたいのではありません。あくまでも私の政治思想的観点からはそういう解釈が成り立つことを知っていただきたいだけです。いうまでもなく、たった一つの正しい解釈があるわけではありません。それどころか観客は各々多様な解釈をするものです。そこで、
2 受講者各人がその映画をどのように解釈したのか、なぜそのような解釈をしたのかを、お互いに説明し理解するよう試みること。
どうしてもご発言されたくない場合やいったん意見を保留したい方には無理強いをいたしましせんが、できれば、出席されるすべての受講者の方々に少なくとも一回は発言いただき、ご自分の解釈とその理由についてご説明いただきたいと思います。そうすることで、同じ作品がどれほど多様な解釈を生み出しうるのか、それはなぜなのか、について全員が自由討論を通じて知ることを目指します。どの意見が「正しい」のかが問題なのではないことにご注意ください。
この作業がなぜ必要なのかといえば、受講者の方々の中には、最終的に自分が創作者となることを目指す方もおられます。その方々が創作者として作り上げる作品が上演される際にも、その作品は観衆の多様な解釈を生むからです。そこで、各映画をまず、創作者としてではなく解釈者として、皆さんに検討し討議いただきたいわけです。その上で、次のステップに移ります。
3 解釈者から創作者の立場へ転換するためのステップとして、討議した映画が従順さからの脱却や不正との対決を目指すよう、聴衆をインスパイアするのに適切といえるかどうか、現代日本や現代世界の問題状況、および創作者自身の思想や価値観に照らして考える。
創作者は、ある創作意図をもって作品を生み出しますが、その作品が作者の意図通りに観客によって解釈されるとは限りません。私がこの講座のために選んだ映画はどれも、従順さの脱却や不正との対決というメッセージを何らかの形で映画作家が意図的に発していると私が解釈したものです。しかし、それは私の解釈であって、皆さんは、このような映画では聴衆をインスパイアするための物語として適切だとはお考えにならないかもしれません。だとすればそれはなぜ不適切なのかを討議する価値があろうかと思います。
この問題についても「正解」はおそらくないでしょう。創作者はそれぞれの人生経験や価値観に基づき、自分が生きる時代状況の中で、どうしても取り上げたい問題に応答すべく自分の意図や狙いを作品として表現することができるだけです。その解釈はもっぱら観衆に委ねられますが、どのような映画が従順さからの脱却や不正との対決というメッセージを発する上で適切だと受講者の方々が考えるかは、その方個人が「従順さ」や「不正権力」という問題に関してどのような価値観や思想を持っているか、また、「今」という時代状況をどのように理解するか、によっても左右されるはずです。それを自ら自覚することは、ご自身の創作活動に役立つことと思います。
以上の三つの課題(とりわけ第二の課題)に取り組むに際して、次の問題を念頭において映画を鑑賞してください。
1 この映画がプロットとして提示する問題状況は何か。
2 その問題状況への主要登場人物による対応はどのようなものだったのか。なぜそのような選択・行動を取ったのか。
3 以上のような問題状況とそれへの対応を描くことで、映画作家は何を意図していたのか。
この三つの問題をめぐって、各セッションを進行したいと考えます。皆さんの積極的なご参加を期待します。